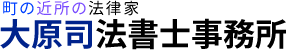相続登記は自分でしても問題ない?判断基準や手続きの内容を解説
カテゴリ:司法書士コラム
相続登記は2024年4月から義務化され、相続に伴い家屋や土地を取得するときは必ず登記申請の手続きをしないといけなくなりました。このとき、司法書士に依頼するか自分で行うか迷われる方もいるかと思います。
実際のところ、法的知識がなくても問題ないケースはあります。一方で相続の状況によっては難易度が大きく変わり、リスクが大きくなるケースもあるため注意が必要です。自分で対応する場合どのような手続きに対処しないといけないのか、どんな場合に司法書士に頼んだ方が良いのか、ここで解説します。
司法書士への依頼を考える判断基準
相続登記を自分で行っても問題ないか、司法書士に依頼すべきか、その判断の基準として、相続関係の複雑さや不動産の状況、そして相続人間の関係性やご自身の時間的余裕などに着目すると良いです。相続関係や財産状況がシンプルで複雑な事案でなければ難易度はそれほど高くなりませんし、作業にあたる時間的余裕もあるならご自身で対応することも視野に入ってくるでしょう。
以下2点については特にチェックしておくべきです。
相続関係は複雑か
「相続人の中に行方不明者がいる」「認知症などで判断能力に問題がある相続人がいる」「相続放棄をした人がいる」などの場合には、通常の手続きに加えて特別な対応が必要になります。
行方不明者については不在者財産管理人の選任を、判断能力に問題がある場合は成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続放棄をした人については相続人ではないものとみなされることから、相続放棄をした人を把握するなど遺産分割協議への参加者をよく確認する必要があるでしょう。
また、被相続人に隠し子がいるかもしれない場合や養子縁組を行った過去がある場合なども、相続人の確定作業が複雑化します。このような状況にあるなら家事事件に詳しい司法書士に対応を依頼することをおすすめします。
不動産は複数あるか
相続する不動産が複数の都道府県にまたがっている場合、それぞれの管轄法務局で手続きを行う必要があります。また、農地や山林が含まれている場合は、農業委員会への届出や立木の評価など、特殊な手続きが必要になることがあります。
マンションなどの区分所有建物に対しては土地(又は敷地権)と建物それぞれの登記が必要ですし、持分の計算も複雑です。借地権付きの建物、共有持分のみの相続などの場合も、専門知識がなければ対応に困る手続きに直面する可能性が高くなります。
基本的な手続きの流れ
もし相続登記を自分で進めるなら、全体の流れを把握しておくことが大切です。
大きく分けて①書類収集、②申請書作成、③法務局への申請の3段階に分かれます。各段階でしないといけないことを以下にまとめましたので、ご自身で対応できそうかご確認ください。
必要書類の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書、不動産相続人の住民票の写し、が基本な準備書類となります。被相続人の戸籍については、転籍や婚姻により複数の市区町村にまたがることもありますが、それらすべてを漏れなく取得する必要があります。被相続人の直系血族または配偶者であれば、広域交付制度を利用すれば、最寄りの市町村窓口で一括して取得できます。
また、不動産の固定資産評価証明書(登録免許税の計算のため)や登記事項証明書(申請書の記載内容の確認のため)も準備が必要です。遺産分割協議を行った場合は、相続人全員が署名押印した遺産分割協議書も備えなければなりません。
一つひとつは単純作業であっても、多くの時間を要することが問題となるケースが多いです。平日に各種役所を回る必要があることも考慮しておきましょう。
申請書の作成
登記申請書の作成は、法務局のホームページにひな形が掲載されているため、それを参考に進めることができます。しかし、相続の形態(遺言による相続、法定相続、遺産分割による相続)によっても記載方法が異なり、ご自身の状況に合わせて適切な書き方をしないといけません。
記載ミスが補正を求められ、再度法務局に出向く必要が生じます。たとえば不動産の表示に関する部分は、登記事項証明書の記載と一致させる必要があり、差異があると受理されません。登録免許税の計算も正確に行い、法定の計算方法により算出した金額を納付します。
法務局への申請
集めた添付書類、作成した登記申請書など、必要書類一式が整ったら不動産所在地を管轄する法務局に申請を行いましょう。
申請方法は窓口持参、郵送、オンライン申請の3つです。オンラインであれば直接出向く必要がなく楽ですが、窓口でも、軽微なミスをその場ですぐ補正できる場合があるため利点はあります。
申請後は法務局での審査が行われ、通常1〜2週間程度(混雑状況によってはより長い期間)で登記が完了。交付された登記識別情報通知書は大切に保管しておきましょう。もし補正が必要なら法務局から連絡を受けますので、指定された期限内に対応します。
相続登記の手続きにミスがあった場合のリスク
ご自身で対応すれば専門家への依頼費用を浮かせることができます。しかしながら、相続登記のミスには次のリスクが伴うことも認識しておいてください。
相続登記が正しく行われない場合のリスク | |
|---|---|
過料(ペナルティ)を科される | 相続登記は法律上の義務となっており、3年以内に対応しなければ10万円以下の過料が科されるかもしれない。 |
売却・担保設定が困難になる | 登記簿上の所有者と実際の所有者が一致しないなど登記内容に誤りがあると、不動産を売却したり、借入のための担保設定をしたりするのが難しくなる。 |
権利関係が複雑化する | 適切な登記ができないまま相続人が亡くなると、その配偶者や子どもが新たな相続人となり、さらに関係者が増えて権利関係が複雑化する。 |
第三者からの権利侵害の可能性 | 不動産に対する権利を主張する第三者が現れたとき、登記が適切に行われていないと当該物件を守れない可能性が高まる。 |
登記手続きに自信がない、対象不動産の価額がとても大きい、といった場合には司法書士の活用も視野に入れていただくと良いでしょう。