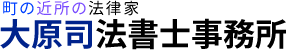相続登記の相談事例から
カテゴリ:司法書士コラム
相続登記については、令和6年4月から義務化されて、それ以前に開始した相続についても同様に、相続登記を申請しなければいけなくなったので、相談が増えています。
そんな中で、普段はあまり見られない相談がありましたので紹介します。
関係者
Aさん 平成30年没 妻Bさんとの間にお子さんはいない。
Bさん Aさんの妻で、本件の相談者
Cさん Aさんの姉で、令和6年没だが生涯独身で法定相続人はいない。
Bさんは、Aさん所有の不動産について、相続登記は未了だが、Aさんの代表相続人として固定資産税を支払ってきていた。Cさんが亡くなり、そろそろ相続登記をしたいと相談してこられた。Bさんとしては、Cさんが亡くなってAさんの法定相続人は自分一人になったので、相続登記は簡単にできると思い、必要書類を知りたいとのことであった。
しかし、
- Aさんが死亡した平成30年時点で、妻のBさんが4分の3、姉のCさんが4分の1という法定相続が発生しており、別途遺言や遺産分割協議がなされていなければ、不動産はこの割合での共有状態になっている。
- BさんにもCさんにもこのような認識がなく、ずっと夫婦で暮らしてきた不動産については、当然にBさんが相続するものというつもりであった。このため、遺産分割協議などは思いもよらないことであった。
- その状態のまま、Cさんが平成6年に亡くなったので、Cさんが有していた相続分4分の1については、法定相続人が存在しないため宙に浮いてしまい、Bさんが相続人として取得するのは困難になった。
高齢者が関係する相続については、一世代前から相続登記が未了で、数次相続で法定相続人が多数にわたり、親族同士があまり親交がなく、遺産分割協議に手間取ったり、あるいは代襲相続が発生したりと、当事者多数の事例が多いのですが、今回のように一見単純に見える事例でも、当事者の思い込みによる遺産分割協議漏れ、という事態があるようです。
この事例では、Cさんの法定相続分についての相続財産清算人を申立て、相続財産清算の手続きを経て、BさんはCさんの特別縁故者として認めてもらい、持分移転登記をする必要があります。これは相当面倒でハードルの高い手続きになります。
相続財産清算人とは?相続財産管理人との違いや選任の流れを解説 | 相続弁護士 ドットコム
本件のような事態を未然に防ぐためには、AさんがBさんへの遺言を残されるのが一番良かったわけですが、そうでなくてもAさんの相続手続きの際に、Bさんの身になって、どういう手続きが必要になるかをアドバイスしてくれる専門家がいればよかった、ということは言えると思います。
なので、少しでも気になる点がありましたら、お近くの専門家(弁護士、司法書士、税理士など)にご相談ください。