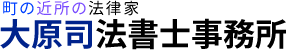特別受益とは?相続分や遺留分への影響と具体例を紹介
カテゴリ:司法書士コラム
相続人が多額の生前贈与を受けていたとき、その利益分が「特別受益」となり、相続分が少なくなってしまうことがあります。
遺産の取り分については争いが起こることもありますので、過去に贈与を受けていた相続人、贈与を受けられなかった相続人、どちらも特別受益について知っておくことが望ましいです。
そこで当記事ではこの特別受益の概要と相続分等への影響、また、具体例についても取り上げて解説をしていきます。
特別受益とは
特別受益とは、生計の資本などとして過去に贈与された財産あるいは遺贈のことです。被相続人(亡くなった方)のしたすべての贈与が対象になるわけではなく、少なくとも受贈者が相続人である場合に特別受益と呼ばれます。
また、相続人が贈与を受けていたとしても特別受益になるもの・ならないものがあり、一つひとつ贈与の目的や贈与額の大きさなどを評価していく必要があります。線引きが明確でないことから、特別受益をめぐってトラブルになるケースもあるため要注意です。
特別受益による相続分への影響
財産を与える行為を特別受益として法律で定めているのは、「相続人間の不平等の是正」が目的です。そこで特別受益と評価される場合、当該財産を遺産の先渡しと捉えて、相続分を調整する取り扱いになっています。
「持戻し」により取り分が減る
特別受益を受けていた相続人は、その分相続で取得できる遺産が少なくなります。このルールは民法に定められています。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、・・・相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
本来は、遺産の総額に法定相続分を乗じて個々の相続分が算出されます(例1)。しかし、特別受益があるときはその分を遺産の総額に加算し(持戻し)、最後に特別受益分を控除しないといけません(例2)。
例1:遺産の総額が1億円で、配偶者と長男が共同相続する。
長男の相続分 = 遺産の総額×法定相続分
= 1億円×1/2
= 5,000万円
※配偶者も同じになる
例2:遺産の総額が1億円で、配偶者と、過去に特別受益3,000万円を受けた長男が共同相続する。
長男の相続分 = (遺産の総額+特別受益)×法定相続分-特別受益
= 1億3,000万円×1/2-3,000万円
= 3,500万円
配偶者の相続分= (遺産の総額+特別受益)×法定相続分
= 1億3,000万円×1/2
= 6,500万円
この計算式からわかるように、単純に「相続分5,000万円-特別受益3,000万円」の計算をしているわけではありません。
なお、共同相続人がともに同程度の特別受益を受けていたときは、わざわざ持戻しによる計算を行わないことも多いです。
また、上述の通り持戻しの対象となるのは相続人に対する贈与ですので、当該相続人の家族に贈与があったとしても特別受益として換算はしません。
遺言書で「持戻し」は免除できる
特別受益があるときの「持戻し」は、常に強制されるわけではありません。
被相続人が「持戻しはしない」と意思表示をしていたなら、その通りに効力を生じさせることができます。そこで遺言書にその旨記されているときは、特別受益にあたる贈与があったとしても相続分が減ることはありません。
配偶者は「持戻し」が一部免除される
持戻しは、被相続人が免除の意思を明示したときのほか、配偶者が受贈者であるときの特定の贈与についても免除されます。
持戻しが免除されるのは次の要件を満たす場合です。
- 配偶者に対する贈与や遺贈である
- その配偶者との婚姻期間は20年以上である
- 贈与や遺贈の対象物が居住用の建物またはその敷地である
住まいとしての不動産を配偶者に与えるのは珍しいことではなく、その他相続人との間で特別不平等と呼べる行為でもありません。にもかかわらずこれを特別受益とみなして持戻しをしたのではその後の生活資金が得られなくなるなどの問題が生じます。そこで法律上、免除の推定が働くと規定されているのです。
特別受益は遺留分にも影響する
特別受益の影響は「遺留分」にも及びます。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に留保される、最低限の遺産の取り分です。遺贈により財産がほとんど受け取れないような場合は、遺留分権利者が「遺留分の侵害を受けたから、その侵害額を請求する」と主張することで受遺者等から金銭の支払いを受けることができるのです。
もし、配偶者と長男が共同相続するのであれば、それぞれ1/4ずつまで遺留分として主張することが可能です。計算の基礎となる財産の総額が1億円であれば遺留分は2,500万円です。実際に取得できたのが500万円だとすれば、遺留分侵害額である2,000万円を受遺者に請求できることとなります。
しかしながら、過去に特別受益2,000万円以上を受けていたのであれば、その分控除されるため遺留分侵害額請求はできなくなります。(仮に持ち戻し免除があっても遺留分の計算には影響しません)
特別受益になるもの・ならないものの例
最後に、特別受益になるものとならないものの例をいくつか紹介します。「〇〇万円以上の贈与は特別受益」「△△を贈与したときは特別受益」などと画一的な区分はないことに留意しましょう。
特別受益になるものの例 | |
|---|---|
結婚持参金や支度金 | 多額の贈与は遺産の前渡しとみなされることが多く、結婚持参金や支度金などは特別受益になる例が多い。 |
住宅購入のための支援金 | 子どもや孫が住宅を取得するとき、多額の贈与をすることがある。この支援で渡した金銭が特別受益になるケースがある。 |
不動産の贈与 | 土地の贈与なども価額が大きく特別受益になりやすい。 |
株式や事業用資産の贈与 | 経営者の被相続人が子ども等に株式や事業用の土地などを贈与したとき、特別受益にあたることがある。 |
特別受益にならないものの例 | |
生命保険金 | 生命保険金は純粋な相続財産ではなく契約に基づいて受け取る金銭であり、特別受益にはならない。 ただし相続税の計算においては相続財産としてみなされることに注意。 |
死亡退職金 | 死亡退職金も純粋な相続財産ではなく特別受益にはならない。 ただし相続税の計算においては相続財産としてみなされることに注意。 |
生活費の仕送り | 子どもに対する生活費の仕送りなど、扶養義務の範疇で行われる援助はそもそも贈与にあたらず、特別受益にならない。 |
一般的な教育費用 | 高校や大学で教育を受けるために必要なお金については、これを与えても特別受益にはならない。特別多額の資金を与えている場合には例外的に特別受益になる。 |
結納金や挙式費用 | 儀礼的な側面が強い結納金や、葬式費用の援助であれば、特別受益にあたらないケースが多い。 |
金額だけでは決まりませんが、現金を少額で贈与していた程度であれば、それが扶養義務などに基づかない場合でも特別受益としてみなされないことも多いようです。贈与の趣旨、金額、その他様々な点が考慮されますので、判断に迷うときは相続に詳しい専門家を頼りにすると良いでしょう。