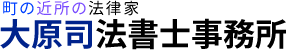後見人を付ける前に知っておきたいメリット・デメリットをわかりやすく解説
カテゴリ:司法書士コラム
認知症や精神障害により判断能力が低下した方を法的に保護する制度が「成年後見制度」です。そして成年後見制度を利用して後見人を付けると財産管理や身上監護において多くの支援を受けられるようになりますが、利用にあたっては慎重な検討が必要です。
制度の仕組みを理解し、メリットとデメリットを十分に把握した上で、本当に必要かどうかを判断しましょう。
成年後見制度の基本的な仕組み
成年後見制度は判断能力が不十分な方を保護するための法的制度で、同制度に基づき家庭裁判所が選任した後見人等が、本人に代わって財産管理や契約行為を行います。
制度には「任意後見」と「法定後見」の2つの種類があります。
任意後見は判断能力があるうちに将来に備えて契約を結ぶ制度です。定められた枠組みの範囲内で保護を受けるのではなく、あらかじめどのような保護を受けようとするのか本人とともに考えることができます。
一方の法定後見はすでに判断能力が低下している方を対象とした制度で、さらに①後見②保佐③補助の3つの類型に分かれます。
類型 | 本人の判断能力の程度 | 後見人等の権限 |
|---|---|---|
後見 | ほとんど判断できない状態 | 「後見人」が包括的に代理権を持つ |
保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 「保佐人」が特定の重要な行為を同意・代理する |
補助 | 判断能力が不十分(保佐ほどではない) | 「補助人」が特定の行為(家庭裁判所の審判による範囲)について同意・代理する |
「後見」がもっとも利用されている
各類型は実際のところどの程度利用され、どのように利用されているのでしょうか。実情は裁判所HPにて掲載されており、「成年後見関係事件の概況」によれば2024年の後見開始の申し立て件数は28,785件であることがわかっています。
保佐は9,156件、補助は3,026件、任意後見(監督人の選任)は874件ですので、成年後見制度のうちもっとも利用数が多いのは後見であるとわかります。
そこでここからは、成年後見制度の中でも主要といえる後見について詳しく見ていきましょう。なお、現在もっと使いやすい制度にするための見直し議論が進んでいますが、基本的な構造は変わらないと見られるので、現行制度を前提に解説します。
後見人を付ける主なメリット
後見人の選任は、判断能力が低下した方とその家族に多くのメリットをもたらします。特に財産の保護や法的手続きの面で大きな安心感を得られるでしょう。
適切な財産管理の実現
「本人の財産を守れるようになること」が、後見人を付けることの一番のメリットといえるでしょう。
後見人は本人の預貯金や不動産などさまざまな財産状況を整理し、生活に必要な支出を適切に管理します。
認知症が進行すると通帳や印鑑の管理が難しくなったり金銭感覚が変わってしまったりするケースもありますが、後見人が財産管理に対応することで財産を保護できるようになります。
また、後見人には家庭裁判所に定期的な財産状況報告を行う義務が課されているため、財産管理に対する透明性も一定程度確保されています。
法的手続きの代行
判断能力が低下することでさまざまな手続きが単独でできなくなってしまいます。しかし後見人が選任されることで、生活に必要な手続き、契約行為なども本人に代わって実行してもらえるようになります。
たとえば銀行での入出金や口座解約、不動産の売買契約、介護施設への入所契約、遺産分割協議への参加など、認知症が進行してからでは対応が難しい行為にも対処可能です。特に、高齢者施設への入所費用を確保するための不動産売却、医療費支払いのための預金引き出しなどに対応できるようになるのは、本人とその家族にとって大きなメリットとなるでしょう。
その上、本人の居住用不動産の売却などリスクも伴う行為に関しては家庭裁判所の許可が必要とされますし、後見人が好き勝手何でもできるようになるわけではありません。
悪徳商法や詐欺から守れる
高齢者を狙った詐欺や悪徳商法に関するリスクは判断能力が衰えるほど高まりますが、後見人が選任されていれば、被害を受ける可能性を下げることもできます。
本人が誤った判断により法律行為を行ったとしても、後見人が取り消すことができると法定されているためです。
※日常生活に関する軽微な行為については取り消せない。
訪問販売や電話勧誘による高額商品の購入、不必要なリフォーム契約、投資詐欺などの被害も防ぎやすくなるでしょう。
後見人を付ける主なデメリット
成年後見制度の利用は、本人や家族に負担となる側面もあります。デメリットもよく理解し、利用前に十分検討するよう努めましょう。
継続的に費用がかかる
忘れてはいけないポイントの1つが「費用」です。
まず、後見人を選任してもらう際の申し立てとその準備に費用がかかります。しかし申し立て段階の費用は大きなものではなく、留意したいのは制度利用後に継続的に発生する費用負担の方です。
後見人はその後本人のために仕事を続けることになりますので、職務に対する報酬が発生し、その負担を本人の財産から支出しなくてはなりません。
報酬額は本人の財産額等に応じて家庭裁判所が決定しますが、通常、月額2万円~6万円程度が発生するでしょう。
資産運用や承継に対する制約がかかる
成年後見制度は「本人の財産を保護・維持すること」を重視していますので、その趣旨に反する行為やリスクある積極的な財産活用などは原則として後見人でも対応できません。
そこで以下のような行為は家庭裁判所の厳しいチェックを受けることになる、もしくはそもそも許可されず実行できなくなるでしょう。
- 不動産の売却・賃貸・リフォーム
・・・本人の介護費用捻出のためであっても裁判所の許可が必要。 - 生前贈与
・・・相続税対策として子どもや孫などに財産を無償で与える行為は、本人の財産を減少させるため原則認められない。 - 資産運用
・・・株式や不動産投資など、リスクの大きな資産運用は原則認められない。
成年後見の解除は困難
成年後見制度をいったん利用し始めると、原則として解除はできません。
本人の判断能力の低下を理由に開始されますので、その状態が続いている限りは家族の総意でも後見人を解任させることができません。
また、家庭裁判所が選任した後見人が気に入らない場合でも性格の不一致程度だと変更できず、不正行為や業務怠慢など重大な問題がある場合にのみ変更が認められます。
申し立て前に検討すべきポイント
成年後見制度の申し立てを行う前に、上記メリット・デメリットを踏まえて慎重に検討を進めましょう。また、その際は以下のポイントを整理しておくと良いです。
検討事項 | 着目するポイント |
|---|---|
制度利用の必要性 | 本当に成年後見制度が最適かどうか。ほかの方法(任意後見・家族信託等)も比較検討して現状にもっとも適しているかどうかを評価する。 |
申し立てのタイミング | 開始まで数ヶ月程度はかかることが多い。本人が判断能力を欠いている状況ならリスクが大きいため、早めの準備が重要。 |
費用負担の見通し | 申立費用、そして後見人に対する報酬が長期的に続くため、家計や本人財産への影響を事前に試算しておくと良い。 |
後見人の選定 | 希望通りにいかない可能性もあるが、指定した親族を後見人とできるケースもある。ただし職務への対応には高い専門性が求められるため、司法書士など信頼できる専門家を選任することも要検討。 |
以上の点も考慮すると、より適切な判断ができるようになるでしょう。