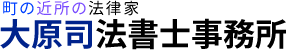不動産登記の種類について|所有権移転や抵当権抹消、相続登記などを紹介
カテゴリ:司法書士コラム
不動産の権利関係を示す公的な仕組みが「登記」です。売買や相続、住宅ローンの設定など不動産に関する重要な権利の設定や変更があるときは不動産登記を行うことになりますが、登記を行う理由に応じて登記の種類は異なります。
ここでは不動産登記にどのような種類があるのか、主なものを取り上げて紹介していますのでぜひご確認ください。
不動産の登記とは
「不動産登記」とは、土地や建物の所在・物理的状況及び所有者や権利関係を公的に記録・示す制度のことです。
たとえば、新築マンションを購入した際には所有権保存登記を行い、中古物件を買った場合には所有権移転登記を行います。この手続きを行うことで、その物件の正当な所有者であることを第三者にも主張できるようになるのです。
なお、登記には大きく分けて「権利に関する登記」と「表示に関する登記」の2種類があり、前者は所有権や抵当権などの権利関係を、後者は不動産の所在地や面積などの物理的な状況を示すものとなっています。
権利に関する登記について
不動産に関する権利変更を公示する「権利に関する登記」には、所有権移転や抵当権の設定などがあります。これらの登記は、申請が任意とされているものと義務的なものに分かれていますが、いずれにしろ早めに登記を済ませておくべきといえるでしょう。
所有権移転登記
「所有権移転登記」とは、不動産売買・相続・贈与・離婚による財産分与など、所有者の変更を公示するために行う登記です。
相続登記を除いて法律上の義務ではありませんが、登記を行わないと第三者に対して所有権を主張できず、将来的な売却や担保設定も困難となってしまいます。また、未登記のまま相続が発生してしまうとその後の手続きが複雑化するため、所有権を取得したなら速やかに申請することが推奨されます。不動産売買では代金決済と同時に行われますのが一般的です。
登記申請に使う書式とその記載例が法務省HPに掲載されています。こちらを確認すると申請のために必要な情報が確認できるでしょう。
※贈与、財産分与などの違いによって書き方は異なる。
所有権保存登記
「所有権保存登記」とは、新築建物の完成時や未登記不動産の所有権を明確にする場合に行う、初めての所有権の登記です。
建物の場合、まず表示登記を行った後に所有権保存登記を申請するという流れとなります。任意の手続きではありますが、この登記を行わないとやはり所有権の公示ができず、将来的な不動産取引や住宅ローンの利用に支障をきたす可能性が高くなってしまいます。また、建物の登記がない場合、その建物を担保とした融資を受けることが困難です。
所有権保存登記申請で使う書式・記載例はこちらから確認できます。
抵当権設定登記
「抵当権設定登記」とは、住宅ローンや事業資金の借入時に、不動産を担保として提供する際に求められる登記のことです。
法律上の義務ではありませんが、融資実行の条件として金融機関から要求されるのが一般的です。この登記がなければ借入自体ができず、また担保権を第三者に対抗することも困難となるでしょう。金融機関借入では金融機関側で登記申請するのが一般的です。
抵当権設定登記申請で使う書式・記載例はこちらから確認できます。
抵当権抹消登記
「抵当権抹消登記」とは、住宅ローンなどの債務を完済した際、不動産に設定されていた抵当権を抹消するために行う登記のことです。
抵当権抹消登記の手続きは通常、債務者(所有者)と債権者(金融機関)の共同申請により行われます。完済後、自動的に抵当権が消えるわけではないため、金融機関から交付される書類をもとに申請を行いましょう。
抵当権抹消登記申請で使う書式・記載例はこちらから確認できます。
住所変更の登記
「住所変更の登記」とは、引越しや住居表示の変更により不動産所有者の住所が変わった場合に行う登記のことです。
法務局からの重要な連絡が届かなくなるほか、将来の取引や相続手続きが複雑化するリスクがありますので、住所変更があったときは必ず申請するようにしましょう。
また、法改正を受け、2026年4月からは住所等変更の登記が義務となります。2026年4月以前に変更があった場合でも新ルールに従い登記申請が必須ですので要注意です。
住所変更の登記申請で使う書式・記載例はこちらから確認できます。
※住所移転の場合における記載例。
氏名変更の登記
「氏名変更の登記」とは、結婚や離婚による改姓や名前の変更があった場合に行う登記のことです。
住所変更の登記と同様、法改正により義務化が予定されていますので、変更が生じたときは必ず申請を行うようにしましょう。
なお、氏名変更と住所変更の登記は1つの申請でまとめて行うことができます。
氏名変更の登記申請で使う書式・記載例はこちらから確認できます。
建物滅失の登記
「建物滅失の登記」とは、建物の解体後、その建物が存在しなくなったことを公示するために行う登記のことです。
こちらの登記に関しては解体から1ヶ月以内の申請が法律で義務付けられており、これを怠ると過料が科される可能性がありますので要注意です。
またペナルティとは別に、登記を行わないことで土地の売却や建て替えが難しくなってしまうなど事実上の問題にも直面します。火災や災害により建物が消失した場合も同様に登記を行うようにしましょう。
※建物の一部滅失のケースでは登記申請は義務ではなく任意。
建物滅失の登記申請で使う書式・記載例はこちらから確認できます。
表示に関する登記
不動産の物理的な状況を公示する「表示に関する登記」は、土地や建物の所在地、面積、構造などの客観的な情報を示すためのものです。
新築時の建物表示登記や土地の分筆・合筆登記などがこれに該当します。これらの登記は、不動産の物理的な現況と登記記録を一致させることで、取引の安全性を確保する重要な役割を果たしています。
なお「不動産の表示に関する登記」は、物件の現況を迅速・正確に示す必要性が高いことから、一部の手続きを除いて“物理的状況が変わった日から1ヶ月以内”の申請が原則とされています。申請が法律上の義務である点にはご注意ください。
「相続登記」とは
不動産の所有者が亡くなり、相続を理由とする所有権の移転が起こったときの登記を指して、「相続登記」と呼ぶこともあります。
一般的な所有権移転登記であれば法律上の義務ではありませんが、相続により取得したときは登記すべき義務が課されます。これは2024年4月からの新ルールによるもので、自己のために相続があったことを知ってから“3年以内”に申請を行わなければなりません。この期限を過ぎると過料として10万円以下の支払い義務が課される可能性があります。
ただ、相続の場合は遺産分割協議が進まないと新所有者もなかなか定まらず、期限までに申請義務が果たせないおそれもあります。そこで、簡易な方法によりいったん申請義務を履行したものとできる「相続人申告登記」の仕組みも設けられています。
※これにより過料のリスクを回避できるが、その後遺産分割が完了したときは改めて正式な相続登記をしないといけない。
相続登記の申請で使う書式・記載例はこちらから確認できます。
※こちらは法定相続分に従った取得を想定したもの。遺産分割、遺言、遺贈など、具体的な事情によって申請の方法は若干異なる。
配偶者居住権に関する登記もある
相続開始時に配偶者が居住していた建物であれば、終身または一定期間、無償で居住ができるとする「配偶者居住権」が法律上認められます。
被相続人の配偶者の生活資金と生活拠点を確保する有益な仕組みですが、登記をしておかないと、建物の所有権を相続したほかの相続人が当該建物を第三者に売却してしまったときにその居住権を主張できなくなる可能性があります。
そこで“建物を所有する人物”に対して、次のように義務が課されています。配偶者居住権を持つ配偶者自身に登記申請の義務が課されているわけではありません。
(配偶者居住権の登記等)
第千三十一条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
配偶者居住権に関する登記の申請書については、こちらから書式と記載例が確認できます。
※こちらは遺産分割により配偶者居住権を設定した場合の記載例。
以上で紹介したように、登記を行う背景に応じて登記申請の仕方にも差異が現れます。不動産に関する権利を守れるかどうかは今後の生活にも大きな影響を与え得る問題ですので、適切な形で登記を行う必要があります。権利に関する登記については司法書士、表示に関する登記については土地家屋調査士に相談するのがよいでしょう。